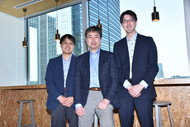「宅急便」で知られ、2019年に創業100周年を迎えたヤマトグループが改革を進めている。 1976年に始めた宅急便は、サービス開始初日は、わずか11個の荷物からスタートした。それから46年後の現在、ヤマト運輸の取扱荷物量はなんと約22億7562万個(2021年度実績)にまで増えた。
預かった荷物をトラックで運ぶ宅急便はこれまで、配送ルートの決定や車両の手配などを社員の経験と勘に頼っていた。しかし不確実性が高い昨今、膨大な量の荷物を効率よく運ぶには、もはや人の力だけでは間に合わない。デジタルの力を活用した、より効率的で無駄のない配送サービスの実現が不可欠だ。
そこでヤマト運輸は「宅急便のDX(デジタルトランスフォーメーション)」に舵を切った。これまで活用できていなかった大量の配送データを使って配送現場の業務を効率化し、企業経営に生かす仕組み作りを進めている。こうしたデータ・ドリブン経営を含むDXの先には、現実世界をデジタル空間に再現したデジタルツインの活用まで見込んでいる。
ヤマト運輸はどう変わっていくのか。今回は“DX請負人”と評され、同社の取り組みを主導しているヤマト運輸の中林紀彦氏(執行役員 DX推進担当)と、改革の中心で活躍するデータサイエンティストの2人に取材した。
社員は約22万人、車両は約5万台 物理的な配送ネットワークを抱えるヤマト運輸の構造改革
ヤマト運輸は46年もの間、宅急便を続けてきた。いまや配送サービスの代表格になった同社を支えるのは、約21万6000人の社員や約5万4000台の車両、全国にある約4000拠点の営業所、約16万7000店の取扱店だ。こうしたフィジカルな接点を結んだ配送ネットワークが、宅急便事業の根幹にある。
しかし大量の物理的なリソースを抱えるヤマト運輸では、その仕組み自体が転換点に来ている。稼働中の配送ネットワークは、宅急便事業を拡大した約30年前に整備したものだ。この配送ネットワークを使う中で、ECサービスの利用増加やドライバー不足といった環境変化に直面した。コロナ禍での宅配需要の拡大もあり、従来の宅急便のビジネスモデルや配送ネットワークを再構築する必要があると中林氏は話す。
物理的なリソースが増えたことで、表面的な改革だけでは十分に効果を得られない。こう判断したヤマトグループは、次の100年を見据えて取り組む経営構造改革プラン「YAMATO NEXT100」 を2020年に策定した。
YAMATO NEXT100は、3つの事業構造改革――「『宅急便』のDX」「ECエコシステムの確立」「法人向け物流事業の強化」と、3つの基盤構造改革――「グループ経営体制の刷新」「データ・ドリブン経営への転換」「サステナビリティの取り組み」で構成している。
経営の根幹を成す事業基盤にメスを入れ、さらに構造改革を進めるこの戦略には、ビジネスのデジタル化では終わらせないという強い決意をうかがえる。この中で中林氏が指揮するのは、DX推進の根幹ともいえるデータ・ドリブン経営への転換だ。
経験と勘に頼った配送オペレーションの改革 データを生かす体制に
「私がヤマト運輸に入った2019年当時、配送現場のオペレーションは個人の経験と勘に頼っており、属人的なものとなっていました。また現場におけるIT基盤の整備は進んでいたものの、日々発生するデータを生かしきれていませんでした。データ・ドリブン経営を推進するには、客観的なデータに基づいた現場オペレーションが必須です」(中林氏)
現場の業務や経営を改革するに当たり、中林氏らはまずデータ・ドリブン経営を支えるデータ基盤「Yamato Digital Platform」(YDP:ヤマトデジタルプラットフォーム)を構築した。
データをほぼリアルタイムで現場に提供 繁忙期の配送を支えた
データ基盤が整ったことで、データをほぼリアルタイムで現場に提供できるようになった。例えば繁忙期では、これまで荷物の配送状況やトラックの位置情報を把握することが難しかった。しかし2021年には約30分に1回のペースでデータを更新した結果、「今日の取扱荷物量はこれで、まだこの量しか運べていない」「別の拠点の社員を一時的に回して今日中に運び終えよう」といった対応ができたと、ヤマト運輸でデータ基盤の開発や運用を担う井口裕太郎氏(デジタル戦略推進部 デジタル開発運用6グループ)は振り返る。
また2021年に始めたEC事業者向けの配送サービス「EAZY」では、EC利用者、EC事業者、配送事業者のデータを一元化することで、精度の高い配送オペレーションを実現できた。荷物の受け取り方法や配送日時を受け取る直前まで変更できるなど、リアルタイム性を生かしたサービスだ。
YDPで最大3カ月先の業務量を予測 社員のシフト作成や車両の手配に活用
ヤマト運輸がYDP活用に最も期待する現場改革が、配送を担う社員のシフト作成やトラックの手配だ。社員のシフト作成や車両の手配は、通常は1カ月前までに済ませる必要がある。これまでは担当者が、過去の取扱荷物量や配車数といった実績を基に手配しており、精度や効率の面で課題があった。個人の暗黙知に頼っており、サービスの品質にも関わる状況だったとヤマト運輸の松本尚貴氏(デジタル戦略推進部 デジタル企画3グループ ミドルエキスパート)は話す。
こうした属人的な体制を変えるために、データと機械学習を活用している。過去の配送データに加えて、季節ごとのイベントや大手EC事業者のセール情報などを基にYDP上で予測モデルを作成。最大3カ月先の業務量を予測でき、社員や車両など経営資源の最適配置を行う狙いだ。
予測結果は、現場の担当者が使いやすいようにBIツールで可視化している。まだ定量的な効果は検証中だが、個人任せだった配送オペレーションの一部に予測モデルを投入することで、確実に工数削減につながっていると中林氏は説明する。
「1カ月前や昨日など過去を振り返る段階から、リアルタイムにデータを見てオペレーションをダイナミックに変える段階まで来ています。さらには、予測に基づいていろいろな施策を先に打ち、最適化する段階に会社全体が移行しています」(中林氏)
データ・ドリブン経営を確立できれば、不測の事態に対応しやすい
データを活用した大胆な改革のマインドは、事業部にも根付き始めている。例えば、配送パートナーと契約する地域やEC向けの配送拠点、オープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」の設置場所などについて、最も効果的な場所を選ぶのにデータを活用している。こうしたデータの可視化と施策を一体化する取り組みが現場で進み、自発的にBIツールを使ってデータベースを活用する動きも増えてきた。
データ・ドリブン経営を確立できれば、ヤマト運輸を取り巻く環境変化にも対応できる。災害やコロナ禍といった予測不能な事態に直面した場合でも、蓄積したデータに基づいた予測モデルの再構築が可能だ。また約5000万人の個人向け会員サービス「クロネコメンバーズ」や約130万社の法人向け会員サービス「ヤマトビジネスメンバーズ」から得た情報を活用し、オペレーションの最適化にもつなげられる。
ヤマト運輸は、物理的な配送ネットワークの効率化が課題だった。しかし、データを活用することでサービス品質や業務の効率化を実現し、環境変化にも柔軟に対応できる体制を整えつつある。
データ基盤に「MLOps」を組み込む挑戦 日本マイクロソフトが支援
ヤマト運輸のデータ・ドリブン経営を後押しするYDPは「Microsoft Azure」上で稼働している。YDP構築時に複数社のパブリッククラウドを比較検討し、Microsoft Azureとデータ分析サービス「Azure Synapse Analytics」を採用した。
もともとヤマト運輸が持っていたデータ基盤はクラウドとの親和性が低く、「YAMATO NEXT100」のデータ・ドリブン経営を進めるにはクラウドネイティブな基盤が必須だった。そこで日本マイクロソフトに相談し、構成の見直しから手伝ってもらったと中林氏は話す。
「データの基盤だけでなく、EAZYやスマートフォン向けアプリなどヤマト運輸が展開しているさまざまなサービスの基盤としても使えるものを目指しました。日本マイクロソフトからは、クラウドネイティブなアーキテクチャのデザインから基盤の構築、実装まで幅広くサポートしていただきました」(中林氏)
さらに今回ヤマト運輸が構築したのは、ただのデータ基盤ではない。機械学習の開発と運用を効率的に進めるための「MLOps」を組み込むチャレンジをした。Microsoft Azureでの前例が少なく、ヤマト運輸が直面した課題を日本マイクロソフトが迅速にすくい上げ、米Microsoft本社と連携するなどきめ細かい対応をしてくれたと井口氏は話す。
デジタルツインの構築を目指す 最適な配送ルートをシミュレーション
ヤマト運輸の取り組みは、伝統的な宅急便を続けながらも、次世代の組織への変革を目指す挑戦だ。データ・ドリブン経営の観点からそれを支える中林氏らが次に目指すのは、デジタルツインの構築と活用だ。
全国にある数千拠点での配送状況や、数万台の車両の運行状況などをデータとして仮想空間に写し取ることで、宅急便ネットワークそのものをデジタル空間上に再現して可視化する。デジタルツインの構築に成功すれば、最適な配送ルートやラストマイル(配送拠点の終着点から利用者に荷物を届ける区間)の効率化を何度もシミュレーションでき、その結果を現実世界に反映して、より一層の改革につなげられる。
データを活用するとはいえ、ヤマト運輸のビジネスは社員やトラックなど物理的な経営資源が必要不可欠だ。配送ルートの設定や拠点の増設に失敗すれば、大きな損失になる。それをサイバー空間上でシミュレーションできれば、大きな成果につながると中林氏は見込んでいる。
100年以上も物流事業を続けている老舗のヤマトグループが、なぜこうした革新的な取り組みを進められるのか。最後に、中林氏に秘訣(ひけつ)を聞いた。
「DXや組織の変革に『これが効く』という特効薬はありません。私たちのように、本業の仕組みに大変革を起こす、次の時代を見据えた体制を作るといった明確な戦略や目的が根底になければ失敗してしまいます」(中林氏)
いまはDXがバズワードのようになっているが、それに左右されずに自社が目指すべき将来像をしっかり描き、その道筋を着実に歩むことが大切だ。そこでは、デジタルやデータの力が必要になり、クラウドの活用やデータ基盤の構築、実装や運用のサポートなどを一貫して支援してくれる日本マイクロソフトは、きっと良きパートナーになるはずだ。まずは自社の未来を考えるところから相談してみるのも良いだろう。
【後編はこちら】
ヤマトで遂げる“データサイエンスの本懐” 約22億個の配送データを分析、そこから経営に貢献 その働き方をのぞく
ヤマト運輸は、地道に荷物を運ぶアナログな企業から、データを活用する次世代の物流企業に生まれ変わりつつある。YDPを使ってデータ・ドリブン経営を進めたことで得た成果は、データサイエンティストやエンジニアの力があってこその取り組みだ。
データサイエンティストの一人は「業務が現場のオペレーションに役立っている実感を持てた」と話す。ヤマト運輸の改革を支えたデジタル人材がどう活躍しているのか取材した。
関連リンク
提供:日本マイクロソフト株式会社
アイティメディア営業企画/制作:ITmedia NEWS編集部/掲載内容有効期限:2022年6月18日
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.